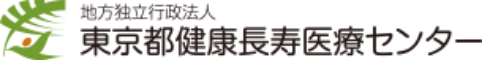研究紹介コラム
高齢者困難事例が抱える困難事象:5つのカテゴリーによる分析的枠組みの提示
Ito K, Okamura T, Tsuda S, Ogisawa F, Awata S.
Characteristics of complex cases of community-dwelling older people with cognitive impairment: A classification and its relationships to clinical stages of dementia. Geriatr Gerontol Int. 2022 Dec;22(12):997-1004. doi: 10.1111/ggi.14494. Epub 2022 Oct 21. PMID: 36269111
認知症支援推進センター センター長 井藤 佳恵

-
1「困難事例」という言葉
「困難事例」という言葉があります。「困難事例」は一義的には定義されませんが、「客観的には支援ニーズがあるのに、接近が困難で、通常のマニュアルに沿った対応が困難な事例」をさして用いられることが多いと思います。つまり、「困難事例」とは、支援者側の支援困難感を基準として用いられる言葉であると考えられます。
-
2「困難事例と言われる人、その本人が抱える困難」という視点
ですが、「支援方策」を検討するためには、支援者の困難感ではなく、本人が抱えている困難に目を向ける必要があります。そのような考えのもと、支援者がもつ支援困難感ではなく、高齢者本人がもつ困りごとという視点で「高齢者困難事例」をとらえることを目的とした研究を行いました。
本研究では高齢者困難事例293人分のデータを用いて、1)認知症等高齢者困難事例が抱える困りごと(困難事象)とはどのようなものか、2)それは認知症が進むことをどのような関係あるのか、ということを分析しました。なお、本研究における「困難事例」とは、「地域包括支援センターの職員が支援困難感をもち、行政機関の介入を依頼した、地域における高齢者困難事例」です。 -
3「困難事例が抱える困難」の5つのカテゴリー
その結果、以下のことが明らかになりました。
- 高齢者困難事例と称される人たちが抱える困難事象は、以下の5つのカテゴリーに分類される:精神的健康の課題、身体的健康の課題、家族の課題、近所づきあいの課題、金銭トラブル。
- 1ケースが抱える困難事象カテゴリー数は、認知症の進展に伴い有意に増加する(p<0.001)。
- 認知症の進行とともに、家族に関する課題(p=0.032) 、近所づきあいの課題(p=0.041)、お金のトラブル(p=0.024)が深刻化する。
- 身体的健康の課題は、認知症の進展よりも、かかりつけ医がいること、つまり持病がある人が(p=0.040)、独居で(p=0.0285)、介護保険サービスをつかっていないこと(p=0.011)と深く関連する。
-
4よりよい支援に向けて
この分析的枠組みを用いることによって、高齢者困難事例が抱える複雑化した困難事象の構造を理解し、より有効な支援方策を打ち出せる可能性があります。板橋区では、高齢者困難事例を対象とした個別支援に、この枠組みを生かしていく体制を整えています。

課題の
種類どんなこと? 例えば? 具体的内容にはどんなこと? 精
神
的
健
康
の
課
題認知症やその他の精神疾患がある、またはあることが疑われ、それが生活を困難にしている*。 未診断の精神疾患(認知症を除く) 認知症を疑うが、未診断で、受診に対する同意が得られない。
診断がつけば、適切な支援方針の立案やサービス導入につなげられる可能性がある。未治療のBPSD(認知症の行動・心理症状) 物とられ妄想などのBPSDを疑う症状があるが、未診断未治療で、受診に対する同意が得られない。
本人の言動がBPSDによるものなのか、あるいはパーソナリティ等によるものなのか、整理ができれば、適切な支援方針の立案やサービス導入につなげられる可能性がある。未診断の精神疾患(認知症を除く) 認知症以外の精神疾患を疑うが、未診断で、精神科受診に対する同意が得られない。
あるいは、精神科診断があるが、治療を中断しており、精神科受診受診に対する同意が得られない。
診断や治療可能性を知ることで、適切な支援方針の立案やサービス導入につなげられる可能性がある。精神疾患の急性期 入院適応ではないかと考える程度の精神症状があるが、精神科受診に対する同意が得られない。
診断や治療可能性の有無がわかれば、適切な支援方針の立案や、医療をふくめた適切なサービス導入につなげられる可能性がある。身
体
の
健
康
の
課
題身体疾患がある、またはあることが疑われ、それが生活を困難にしている*。 身体状態に対する無関心 下肢のむくみ、労作性息切れ、皮膚病変その他、治療が必要な身体疾患があることが疑われるが、受診に対する同意が得られない。
身体状態に対する本人の無関心さや適切な受療行動をとらないことが、精神症状によるものなのか、パーソナリティ等によるものか整理ができれば、適切な支援方針の立案やサービス導入につなげられる可能性がある。せん妄 せん妄を疑う症状があるが、受診に対する同意が得られない。
診断や対応方法への助言があれば、適切な支援方針の立案やサービス導入につなげられる可能性がある。医療機関とのトラブル 医療費未払い、暴言暴力(せん妄時の言動を含む)、妄想にもとづく行動などによって医療機関とトラブルになっていて、必要な受診ができない。
本人の言動が、認知症その他の精神疾患によるものなのか、あるいはパーソナリティ等によるものなのか、整理ができれば、適切な支援方針の立案やサービス導入につなげられる可能性がある。終末期医療の課題 看取りの時期が近いと想定されるが、必要な医療介護サービスの導入に対する同意が得られない。
本人の言動が精神症状によるものなのか、パーソナリティ等よるものか、正常心理として理解すべきことなのか、整理ができれば、適切な支援方針の立案やサービス導入につなげられる可能性がある。家
族
に
関
す
る
課
題家族に関する課題があり、またはあることが疑われ、それが生活を困難にしている*。 身寄りなし 意思決定や契約を代行する人が必要だが、現時点で定まっていない。
本人に代わって契約等の法律行為を行う人を、適切に定めることによって、適切な支援方針の立案やサービス導入につなげられる可能性がある。家族介護者の精神的健康の課題 家族に認知症その他の精神疾患があり、家族の介護力が本人の介護必要度に追いつかない。
要支援者(支援が必要な者)が世帯に複数人いる状態で、世帯全体の課題を扱う必要がある。
誰にどのような支援が必要なのか整理ができれば、適切な支援方針の立案やサービス導入につなげられる可能性がある。家族がサービス利用の阻害因子 虐待とは言えないが、家族の理解不足や支援者との認識の相違により、利用が望ましいサービスを導入できない等、家族がサービス利用の阻害因子になっている。
家族の意向の取り扱いや家族への対応について整理ができれば、適切な支援方針の立案やサービス導入につなげられる可能性がある。虐待 親族による虐待(疑い) 近
所
づ
き
あ
い
の
課
題近隣トラブルがある、またはあることが疑われ、それが生活を困難にしている*。 近隣住民に対する攻撃 本人が、近隣住民や諸機関に対して執拗に苦情を訴える、威嚇する、怒鳴り込む等の言動がある。
本人の言動が精神症状によるものなのか、あるいはパーソナリティ等によるものか整理ができれば、適切な支援方針の立案やサービス導入につなげられる可能性がある。地域社会からの排除 近隣住民、自治会、管理組合等から苦情が寄せられている、立ち退きを求められている、訴訟をおこされている等、地域生活の継続が脅かされている。
近隣トラブルの原因となっている本人の言動が、精神症状によるものなのか、あるいはパーソナリティ等によるものか整理ができれば、適切な支援方針の立案やサービス導入につなげられる可能性がある。いわゆるごみ屋敷 住環境が著しく散らかり不衛生な状況で、近隣苦情が生じていたり、健康への深刻な影響が懸念される。
このような状況に対する、精神機能の影響が整理ができれば、適切な支援方針の立案やサービス導入につなげられる可能性がある。お
金
の
ト
ラ
ブ
ルお金のトラブルがある、またはあることが疑われ、それが生活を困難にしている*。 借金、滞納 家賃滞納による退去勧告、水道光熱費滞納によるライフライン停止、保険料滞納による医療保険や介護保険の使用不能、あるいは年金担保の借金等があり実質生活保護水準以下の生活になっている等。
借金滞納が認知機能低下によるものなのか判断ができれば、適切な支援方針の立案や、制度利用、サービス導入につなげられる可能性がある。経済被害 経済被害(疑い)。
経済被害の背景に認知機能低下があるのかどうか判断ができれば、適切な支援方針の立案や、制度利用、サービス導入につなげられる可能性がある。「生活を困難にしている」 高齢者支援事業では、周囲の人たちとの関係の悪化等、必要なサービスにアクセスできない等によって、本人の地域生活の継続がおびやかされている状態を「生活が困難になっている」状況と定義します。適切な介入によって、本人にとって不利な状況が解消され、認知症や障害の有無によらず、誰もが地域社会に包摂されることを目指します。